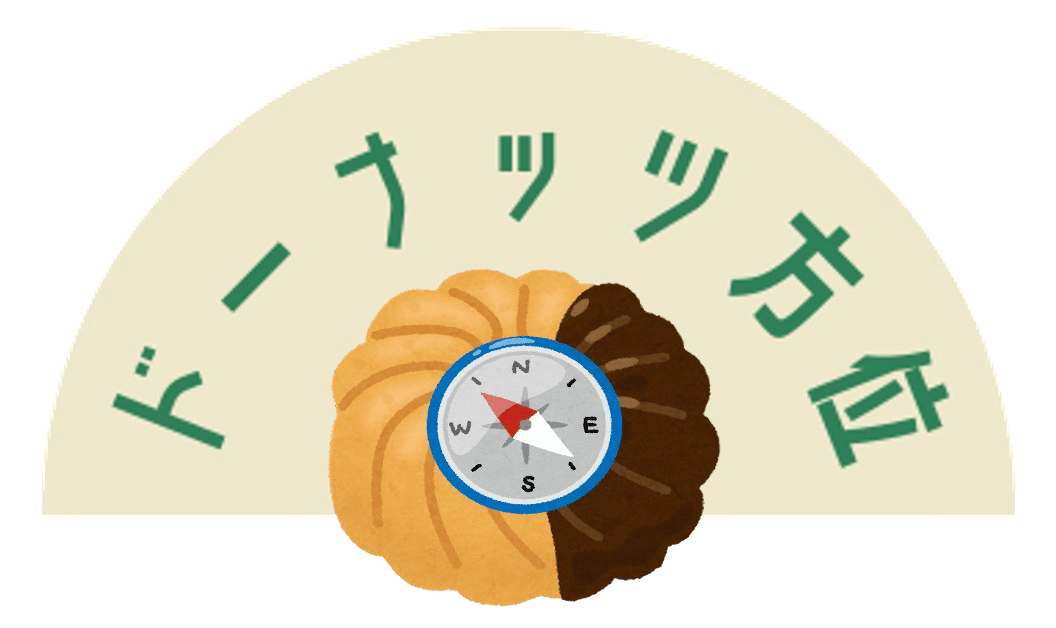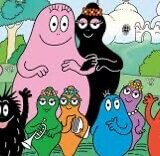ポスト(旧:ツイート)をまとめて見れるサイトがある。ネットの匿名掲示板のまとめサイト同様に結構な頻度で見たりしている。
その中で「コンビーフはイギリス労働者の元気の素。これが無かったら暴力革命が起きていた」というまとめを見た。
牛肉と塩が元気の源になっていたというお話。どこまでが事実でどのくらい盛られた話なのかはわからないが非常に興味深かった。

イギリス海軍名物コンビーフサンド
そのまとめの中の1ポストにも書かれていたのだが”日本の労働者の元気の素が牛丼だった時期がある”と言うものに非常に共感してしまった。
牛丼と言えば「とりあえず牛肉が食べられる」それでいて「早い、安い、美味い」だ。
誤解を恐れずに書くと”吉野家”の一強時代。スマホも無い時代。U字型のカウンターの目の前にはミニ冷蔵スペースがあってそこからお新香とかサラダを勝手にとる。お代は後払いシステムだった。子供や女性がカジュアルに入れる雰囲気はあまりなくサラリーマン、フリーター、酔っ払いなどが手っ取り早く腹に飯を流し込む為に存在していた時代。
そして言い方を恐れずに言えば牛丼は『貧乏めし』だった。当時の牛丼は本当に安く提供されていてバイトで1時間働けばちゃんと大盛りが食べられる感じだった。それでいて腹はちゃんと満たされる魔法の食べ物。ただ決して誇れるような食べ物でもなくグルメ漫画よろしく「いつでも牛丼が食べられる位が人間ちょうど良いってものだ」とはならない。そこは”トンカツ定食”の定位置だ。

目の前に夢のサイドメニューが……!
僕の吉野家のオーダーは「並、卵、味噌汁」が定番だった。今では松屋などはデフォルトで味噌汁がついてくるが、当時の吉野家は別オーダーが必要。でも美味しかった気がする。
豚肉とか鶏肉ではなくて牛肉という所がポイントなのだろうか?確かに僕も幼少期より「牛肉を食べられるのは金持ちだ」みたいな感じで育てられてきた覚えがある。ステーキがその象徴だったからであろうか?余談だが僕は北海道で高校生まで生活していたので焼き肉と言えば、ジンギスカン。羊肉だ。
少なくとも日本での肉の格付けは牛が頂点。わからないけどステーキ、焼肉、しゃぶしゃぶ、すき焼きの全てにおいて牛肉が勝る。それらに比べると豚代表のトンカツや鳥代表の唐揚げはやはり庶民派。
この感覚は世界共通なのかはわからないし宗教の問題もあるだろう。ただ、イギリスは同様の考えということになる。
『貧乏めし』と書いたが、「パンの耳ともやしだけで給料日まで凌いだ」というのともニュアンスは違う。労働者としてサラリーがあり、明日の仕事への元気の素として気軽に食べられると言う感じ。「お金が無くてこれしか食べられない」という感じではないと思う。
牛丼が無かったら日本で暴力革命が起きていたか?と考えるとおそらくそんな事はなかったと思う。日本は食に恵まれた国だ。白米が食べられて、一汁一菜あれば牛丼が無くても大丈夫だろう。……しかし関東に暮らす一人暮らしの若者は仕事が忙しいと必然的に外食に頼りがちだ。それも24時間開いていると残業で深夜になってもついつい牛丼に手が出てしまうので、そういう店が無かったら暴力革命ではなく、仕事の生産性がシンプルに落ちていたのかも知れない。(もしかしたら婚姻率が上がっていたかもしれない)
今はそういう牛丼屋が進化をとげ、牛丼だけでは無くバラエティーに富んだメニューを提供するようになった。一時期、狂牛病と言う牛がかかる疫病があった時代があったがその時は代打、豚。豚丼で屋台骨を支え、牛兄さんを待った。粘り勝ち。
……さてここまで書いておいてあれだが僕はコンビーフを食べたことが無い。スパムミートとかもだ。これをきっかけに食べてみようかななんて思っている。もしかしたら酒のアテかなんかにピッタリとくるかもしれない。ちょっとだけ楽しみだ。僕も労働者なので、とりあえず牛肉なのである。

コンビーフといえばノザキ